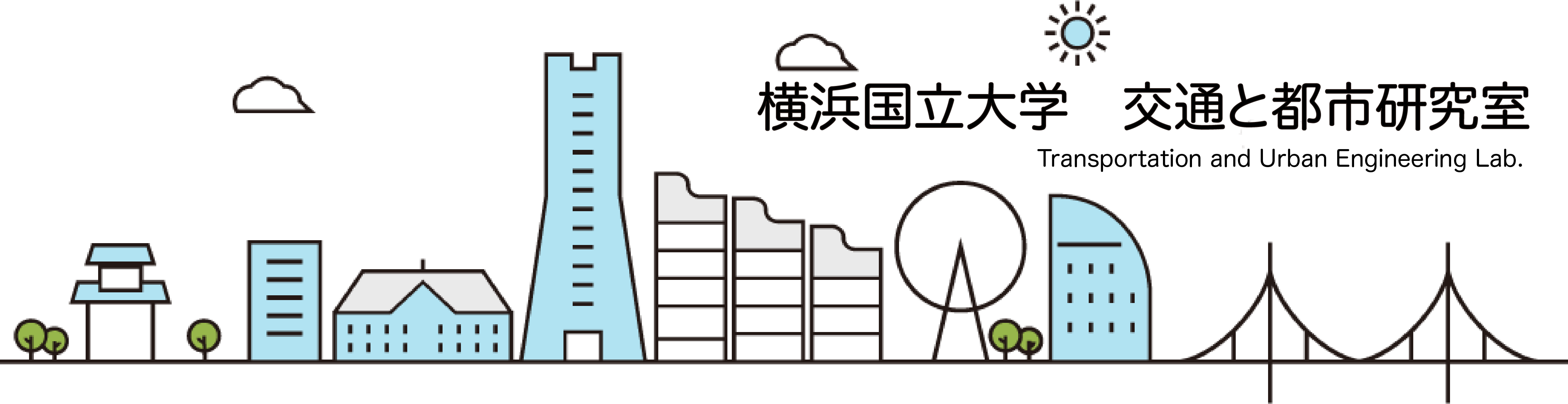日常のようす
研究
研究内容
 当研究室では、学生自身が研究したい内容を提案し、卒業論文・修士論文・博士論文としてまとめています。
近年の研究テーマは、公共交通の運用管理、交通需要マネジメント、都市交通の調査・解析、交通容量、交通事故対策評価、交通結節点周辺の歩行者空間分析など、多岐にわたります。
当研究室では、学生自身が研究したい内容を提案し、卒業論文・修士論文・博士論文としてまとめています。
近年の研究テーマは、公共交通の運用管理、交通需要マネジメント、都市交通の調査・解析、交通容量、交通事故対策評価、交通結節点周辺の歩行者空間分析など、多岐にわたります。
国内に留まらず、アジア都市や南米などグローバルなフィールドを対象地としています。

研究の進め方
2週間に1回程度、研究の進捗状況を担当教員に報告するとともに、研究室会議にて討議の機会を設けています。 ●交通工学研究会研究奨励賞 ●土木計画学研究発表会・春大会・優秀ポスター賞 ●土木学会年次学術講演会・全国大会優秀発表賞受賞者
年に1~2回程度、学会に論文を投稿し、発表します。
・土木学会
・交通工学研究会
・日本都市計画学会
・国際交通安全学会 など
学期末や学年末には、都市地域社会専攻(土木工学)の先生方による研究進捗の審査があります。
メンバーの受賞歴
1997年度 大城温(M2)「バス停留所におけるバス乗降特性とバス交通容量への影響」
2024年度 白岩元彦(M1)
2021年度 池谷風馬 (D2)
2020年度 若原歩花 (M1)
2018年度 福山大地 (M1)
2013年度 平林由梨恵(M1)
2011年度 中本侑香子(M1)
2009年度 森和也 (M1)
2006年度 冨田顕嗣 (M1)
2001年度 松丸未和 (M1)
2000年度 池田久美子(M1)
1998年度 岩上智裕 (M2)
ゼミ活動
英語ゼミ<対象:学部4年、修士1,2年それぞれ>
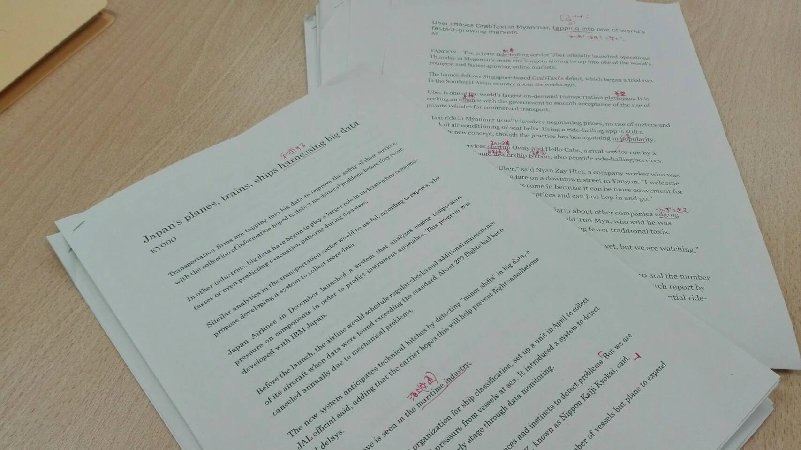 英語のゼミは交通や都市計画に関する英語の記事を訳して紹介するゼミと、交通工学や都市計画に関する英語の教科書を輪読し理解を深めるゼミの2種類があります。
英語のゼミは交通や都市計画に関する英語の記事を訳して紹介するゼミと、交通工学や都市計画に関する英語の教科書を輪読し理解を深めるゼミの2種類があります。
英語や交通と都市計画について学べることはもちろん、日本だけではなく諸外国の観点からも交通と都市計画を学ぶことができます。
学部4年後期及び修士2年の英語ゼミでは、自分の研究に関する英語論文を訳し、説明するという内容になっています。
分析ゼミ<対象:学部4年、修士1年>
分析ゼミは、研究に欠かせない分析について学ぶゼミです。自分たちで集めたデータを実際に扱って分析することで実践的な分析力を身につけることができます。多変量解析について学ぶゼミもあります。
交通工学ゼミ<学部4年>
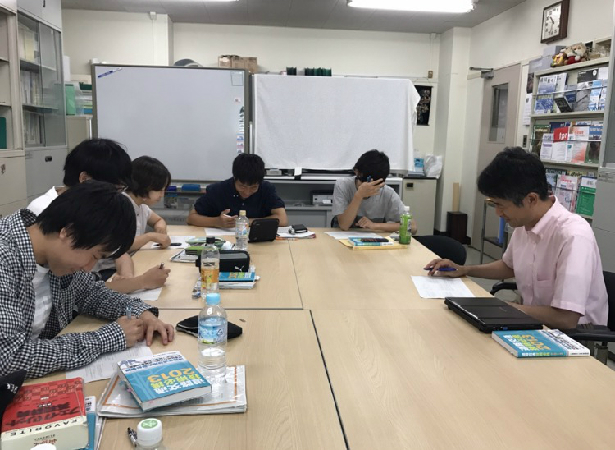
交通工学ゼミは、TOP(Traffic Operations Practitioner certified by JSTE)という、交通技術資格取得を目指し週1で交通工学を学ぶゼミです。学部3年秋学期の交通工学という授業を取っておくと、よりゼミでの理解が深まります。
交通計画ゼミ<対象:学部4年>
交通計画ゼミは、交通計画に関する教科書を輪読し、事前に予習してきた内容をスライドにまとめ質疑を行いながら交通計画を学ぶゼミです。今年度では「交通システム計画(1988) 著:太田勝敏」を輪読しました。
プログラミングゼミ<対象:修士1年>
プログラミングゼミは、R言語というプログラミング言語を基礎から学ぶゼミです。
このページの先頭へ